|
|
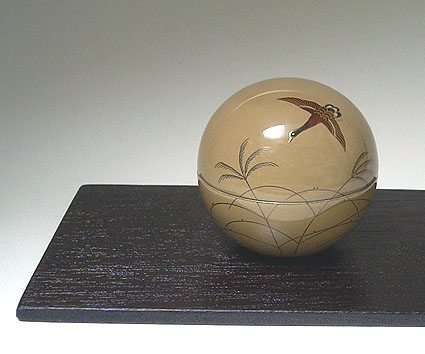
お買上感謝・在庫なし・再入荷なし
らくがんまきえまるなつめ
落雁蒔絵丸棗
25,200円(税込)
申込番号 1252 - 1416
・大多尾重光作・木箱入
・径6.6×高さ6.3cm
※桜材、白漆を使用。
←敷板は撮影小道具
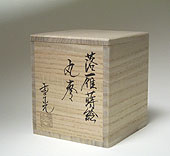
秋の田の 穂田を雁(かり)がね 暗けくに
夜のほどろにも 鳴き渡るかも
聖武天皇 万葉集 巻8-1539
*
夜明け前に飛びゆく雁の鳴き声が
しみじみと・・。

内部は黒。材の木目がやや透ける塗りとなっており、侘びた雰囲気を出しています。
・
ご注文・お問い合せメールはここをクリック



